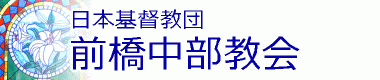〈出エジプト記33章〉,前橋中部教会主日礼拝説教(要旨) 堀江知己牧師
民が悲しんだことは、私たちも悲しまなくてはならないことでした。主が一緒に上ってくださらなければ、民はどうして前に進むことができたでしょうか? しかし、民は悔い改めました。身に着けている飾りを取り去った民でしたが、単に高価な物を捨てたのではなく、もう二度と偶像崇拝は行わないことを誓ったのです。さらに、私たちが悔い改めだけでは足りず、神と顔と顔とを合わせて語り合う執り成し手が私たちには必要です。神が私たちから遠く離れず、そばにいてくださるためには、御子イエスという執り成し手がおられなくてはなりません。まさに御子が世に誕生されたのも、神が共にいてくださるようにするためでした。御子イエスの名がそれをはっきりと示しています(マタ1:23)。とはいえ、神と顔と顔とを合わせて語り合ったはずのモーセでしたが、モーセもまた神の御顔を見ることはできませんでした(20)。顔と顔とを合わせたところで、目が閉じていれば、あるいは目に覆いがかけられていれば、神の御顔を見たことにはなりません(22)。確かに、神が私たちの方に御顔を向けてくださってはじめて、私たちは祝福されます(民6:25)。しかし、不信仰という名の覆いがかかり、私たちは神を直視できません。直視すれば滅んでしまうからです。よって、主の栄光が通り過ぎる時(22)、むしろ岩の裂け目に隠れなくてはなりません。主の栄光が過ぎ去るとは、ここでの場合、災いが降りかかる時、という意味です。その岩とは、岩の上に建てられた教会(マタ16:18)のことです。世に災いが降りかかる時はもちろんのこと、個々人に災いが降りかかる際にも、教会という岩に隠れなくてはなりません。さらに、苦難が過ぎ去った後は、主の後ろ姿を見ましょう。後ろ姿(23)とは、主が助けてくださったあかしという意味です。それを確かめることを通して、あたかも自分を助けてくださった主の後ろ姿を見るかのような気持ちになるでしょう。苦難が過ぎ去るたびに、その都度主の後ろ姿を見るのは、その都度主の御恵みのあかしを確かめ、感謝し、それ以前よりもますます熱心に、主に従うようになるためです。