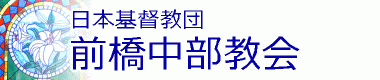【どこにも光があった】(2024年5月5日)
〈出エジプト記9:22-10:29〉,前橋中部教会主日礼拝説教(要旨) 堀江知己牧師
ファラオとエジプト人は暗闇に襲われます。一方で、イスラエルの人々が暮らしていたところには、常に光がありました。「イスラエルの人々が住んでいるところにはどこでも光があった」(23)。教会というところは、まさにそういったところでなくてはなりません。もちろん、教会に光がともっているとしても、それは決して、「世の中には災いが降りかかるけれども、教会は災いとは無縁である」といった意味ではありません。むしろ、世の人は復活の希望を持っていないからこそ、「世は暗闇に覆われている」と表現されます。一方で、教会は、いつも光が輝いていますが、それは、復活と永遠の命への希望が、いつも輝いているからなのです。「あなたがたは世の光である」(マタ5:14)。復活の希望を持つことがないといった点では、世の中は常に暗闇を歩んできました。おそらく、明けの明星――まことの希望の光――が昇るときまで、世はずっと暗いままであるのでしょう。確かに、災いは私たち信仰者をも等しく襲うでしょう。しかし、いつの時代においても、またどこであっても、教会は輝いていなくてはならないのです。これまでもそうであったし、これからもそうであると信じます。「どこでも(=いつでも)光があった」。もし、当時のイスラエルの人々だけに、そして次の災いがエジプト人に降りかかるまでの間だけ、光があっただけならば、私たちにとって、どんな慰めとなるでしょうか? むしろ、常に光があることこそ、私たちにとっての慰めです。私たちの教会も、教勢といった点では、今は悪い時代です。しかし、当時のイスラエルの人々は肉体的にも虐げられ、パンと水に文字どおり事欠いていました。それでも光がいつも輝いていたのです。よって、たとえ困難に直面していても、教会に御光が明るく輝いていることが、私たちにとって一番大切なことですし、一番慰められることです。