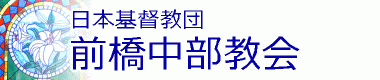【山で語り合っていたこと】(2024年1月14日)
〈ルカによる福音書9:28-45〉,前橋中部教会主日礼拝説教(要旨) 堀江知己牧師
ペトロが仮小屋を三つ建てましょうと言ったのは、主をモーセとエリヤと同列に置いてしまっていたからです。すると、雲が現れて、御声が響き渡り、主のお姿が一人残りました。私たちに、主と同列視してしまうものがあるならば、それらはすぐに御言葉によって消滅しなくてはなりません。主が話し合われていたのはご自身の最期、十字架です。モーセは律法を、エリヤは預言者を象徴します。「律法と預言書」は「(旧約)聖書」の言い換えです。すると、主は、聖書と語り合われていたことになります。何を語り合っていたかというと、ご自身の十字架です。聖書は主の十字架を証ししています。聖書には色々書かれてありますが、一番に何を証ししているかというと、主の十字架です。それを理解していないと、あたかも雲が目の前に現れるようにして、私たちの理解を遮ってしまいます。まるで迷路に入り込み、一体全体聖書は何を告げようとしているのか、訳分からなくなります。さらに、訳分からなくなると、恐怖が涌きます。弟子たちも恐怖を覚えました(34)。私たちも聖書を読む際に、主の十字架を理解していないならば、目を遮る雲が生じ、聖書に関する理解は混乱をきたします。その結果、生じるものは恐怖。主の十字架を理解すると、まるで霧が晴れるかのように、全てを理解できるようになります。「私は十字架以外、何も知ることはない」(一コリ2:2)。パウロは十字架の主を知っていたのですから、既に全てを知っていました。キリストの十字架を知らない人は、他の全てのことを知っていても、何も知ってはいないのと変わりません。キリストの十字架を知らずして、終わりの日について知ったところで、教会を深く愛したところで、何の益があるでしょう? 主は、律法と預言者、すなわち聖書は、神の愛と隣人の愛を説くと教えられました(マタ22:40)。聖書が証しする主の十字架は、神と隣人への愛そのものです。よって私たちは、主の十字架について学ぶとともに、愛の教えに聞かねばなりません。「これに聞け」(35)とのご命令は、十字架によって示された愛の教えに聞け、ということなのでしょう。