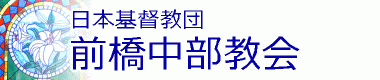【目を細めて見る】(2024年10月13日)
〈ルカによる福音書11:37-12:3〉,前橋中部教会主日礼拝説教(要旨) 堀江知己牧師
誰にも主を招く自由と権利があります。主はファリサイ派の人の家に行かれます。主は身分や教派、主義主張で人を選ぶことはありません。しかし、内面が汚れている人は、主もさすがに招かれるのをお断りされます。主を家に招いた人は、主の行動をチェックしていました。しかし、調べられていたのは彼の方でした。リベカは僕をもてなすことに必死で、自分がチェックされているとは気づかなかったでしょう(創24:21)。僕も、最初は張りつめた目でリベカを見ていたでしょうが、最後には、目を細くして見つめたはずです。この子はなんと気立てが良い子であるかと。主も、この人が神の子どもと見なされるにふさわしいか見ておられました。残念ながら、この人は試験に不合格でした。主に悪を見つけられてしまう前に、自分で自分の心という家の中を調べてみましょう。すると、百人隊長のような気持ちになるのではないでしょうか(マタ8:8)。自分は主を家にお迎えできる者ではないと気づく時にこそ、主は私たちの心に入ってこられます。なぜ律法学者は憤慨したのか? 彼らこそが細かい掟を教えていたからです。彼らが学ぶべきは、つまずかせる者はもっと不幸であることでした(マタ18:7)。主は大勢の人に囲まれます。人々は、本音は軽蔑していたファリサイ派の人々を離れ、この人の方がすばらしいと、主の周りを取り囲んだのではないでしょうか? しかし、主は「ファリサイ派の人々のパン種に注意」と言われます。それは偽善のことです。人から信仰深く、善人とほめそやされるのを望むことも、立派な偽善です。大勢の人に囲まれるとしたら、ファリサイ人ならばどんなにうきうき気分だったでしょう。だから主は言われます。ファリサイ派の人々のパン種には気をつけなさい、つまり、ファリサイ派のように、外面を装って人気を得る人になってはならない、と。偽善を装って多くの人の目を引き付けるよりも、主の御目を引き付けるようにいたしましょう。そして、この人はなんと愛すべき子であるか、というお気持ちがにじみ出た細くした御目で、自分のことを見ていただくようにいたしましょう。